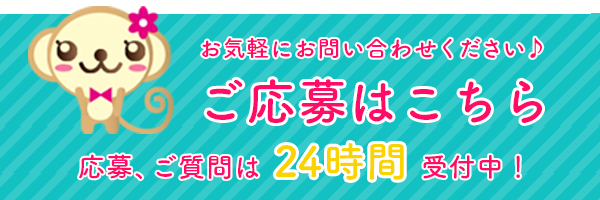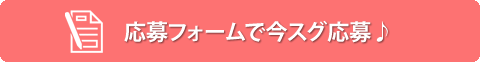チャットレディが書く恋愛小説:そのに
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。前回に続き、読書が趣味のチャットレディの女の子が書いた短編小説の続き、2となります!物語や文章は、基本として、起承転結が重要と言われる事があります。今回の作品は、それに則っていて、今回は起承転結の「承」になるかと。さて、物語は、どんな展開となるのでしょうか・・・?
恋愛物短編小説-2
あの衝撃の一日から一週間が経った金曜日。私はサークルの飲み会に参加するべく、友達と三人で駅前の居酒屋へと向かっていた。就活がひと段落を迎えた四回生の先輩方数人も参加するとのことで、比較的大きな宴会場が押さえられていた。
「ねえ、聞いた? 今日ってあの○○先輩も参加するらしいよ〜!」
「えっ、それほんと?」
「さっき本人から聞いたから間違いないよ」
「ラッキー! 目の保養だよね~」
キャイキャイと興奮して騒ぎ立てる友達に苦笑を漏らす。○○先輩とは、私たちと同じサークルに所属している、この大学内でも随一のイケメンと話題の、四回生の先輩だ。
そんな反応の薄い私を見て、二人がハッとしたように息を呑む。この二人の友達も、私がつい最近彼氏と別れたということを知っているのだ。私の表情にいち早く気が付いた友達が、眉を下げて小さな声で言った。
「あ、ご、ごめん。今そんな気分じゃなかったよね…」
「ううん、そんなことないよ」
それでも途絶えないこちらを気遣う目線に、心が温かいもので包まれたような気分になった。とても友達思いで、心の優しい子たちである。
「……私だって、イケメンの眼福に預かりたいもの」
「何それ!」
キャハハハッ! 今度こそ声を上げて思い切り笑う二人の明朗な笑顔に、私も思わず口端から笑みを漏らしたのであった。
「カンパーイ!!」
凡そ四十人前後が集結した飲み会は、久し振りだということもあってか、飲めや歌えや踊れやと非常に盛り上がった。しかし、私は席が端っこの廊下付近、さらにはそんなにお酒が飲めないということもあって、専ら介抱係に回っていた。
大音量の笑い声が宴会場に響き渡る。ワイワイと盛大に騒いでいる中心の方をチラリと見ると、一際に目立つ男性が目に入った。専ら話題の○○先輩である。
一方で私が座っているこのテーブルは、お酒と料理と会話とを比較的静穏に、ある程度の理性を保ってゆったりと楽しむという人たちが集まっていて、これはこれでとても楽しいように思う。それに、あの輪の中心では、同じサークルに所属している元彼と例の後輩女子が、まるで何事もなかったかのように騒いでいるから、いくら私が行きたいと思っても、気まずくて行けやしないのだ。
トイレに駆け込もうとしてその場の廊下にヨロヨロと崩れ落ちた二回生の女子に、大慌てて駆け寄って体を支えて立ち上がらせる。そんなこんなしていれば、少しの料理とお酒も結局酎ハイ一杯しか飲み食いできていないというのに、あっという間に一時間以上が過ぎ去ってしまっていた。
「そのメイク、似合ってるね」
「!」
不意に耳に入ったその聞き覚えのある声に、ハッと息を呑んだ。話題のイケメン○○先輩が、私の隣に立ってこちらを見下ろしていた。ほろ酔いなのか元よりのテンションなのかは分からないが、頬が僅かに紅潮している。とは言えども、この○○先輩とはサークルでも数度しか顔を合わせたことがないし、片手で数え上げられるほどしか話したことがないのだから、未だ彼のことはよく知らない。
「あ、ありがとうございます」
「前のも清楚で良かったけど、こっちの方が元のパーツがいかされてると思う。美人がより際立ってるよ」
「そんな、褒めても何も出ませんよ」
この濃いメイクが男ウケは最悪だと自覚していたからこそ、そのような評価を受けたことは正直なところ驚きであった。女性慣れしているためもあってか、こういう女の変化とやらには人一倍に敏感なようだ。お世辞かもしれないが、こんな絶世の美男子に褒めて貰えたということは、女としては素直に嬉しい。
○○先輩は、この大学一のモテ男と言っても過言ではない。だからこそ、周囲の人目が気になるというのに、メイクを褒められたことが素直に嬉しくて、思わず私は口元がゆるゆると綻んでしまった。そんな私に、○○先輩もその美しい黒髪を靡かせて頷き、眦を緩めて満足げに微笑んだ。
「けどさ…そういうの、彼氏が嫌がるんじゃない?」
「……」
何気なくそう尋ねられて、思わず笑顔がピシリという音を立てて硬直する。そんな私の僅かな変化に気が付いたのか、彼は「よいしょ」と私の隣にビールジョッキを片手に座り込みながらも、キョトンと首を傾げた。
私がこのサークルに所属する例の元彼と付き合っていたということは、やはり何人かには知れ渡っていたのだ。私は仕方なしに、全ての事情を説明することにした。
「……そ、その、別れたので大丈夫なんです。彼が、もう私のことを、好きじゃなくなってしまったみたいで」
「!」
グワリと目を見開いた○○先輩が、むっつりと黙り込む。眉間に寄せられた皺によって、それまでは穏やかであった彼の雰囲気が、一気に険しいものになった。額と首筋にはメキメキと極太の青筋が浮き上がって、噛み締められた歯がギリリと音を立てる。その目には剣呑な光がゆらりと湛えられていた。彼の全身から迸る激情は、肌がピリピリとした殺意を感じ取る程であり、ぞわりと背中に湧き立った冷や汗がツツ…と体の線を伝い落ちていった。
「あの、変な空気にしちゃってごめんなさい。もう吹っ切れたので、気にして頂かなくて大丈夫ですから」
「……」
私がそう宥めすかそうにも、彼から放出される怒気は止まるところを知らない。○○先輩はしばらくの間、眉間に皺を作ったまま押し黙っていたが、ようやく彼の表情がフッと融解するように和らいだ。
「……ふぅん。ってことは、もうあの男に未練はないんだ?」
「は、はい」
にんまり。突如唇を吊り上げてほくそ笑んださんが、テーブルの上に置かれていた私の手に、そのゴツゴツと筋張った大きな手を覆い被せた。突然の触れ合いに驚愕して思わずパッと顔を上げると、目鼻立ちがくっきりとした日本人離れした容姿端麗な顔が傍にあって、私は思わず体を退け反らせた。しかし、そのまま指を絡ませるように手を握り締められてしまい、反対の手で右腰をがっしりと鷲掴みにされて、身動きが取れなくなった。
「えっ、○○、さん…?」
一体、何が起こっているのだ。思考が完全に停止する。口をパクパクとさせるが、驚愕のあまりに全身の筋肉が硬直して、まともな言葉が出て来ない。
「…なら、これからは遠慮なく口説いていいってことかな?」
……。ん? 今何て?
その言葉を何度も何度も反芻して、ようやく意味を理解した。目と鼻の先でこちらを見つめる○○先輩の熱っぽい漆黒の瞳に、頬が真っ赤に染まり上がる。まるで燃え滾る炎に当てられたかのように全身が熱い。
目の前の彼のことで頭がいっぱいになっていた私は、私の背後で呆然とした様子でこちらを見つめている元彼を、私の背中越しに○○先輩が恐ろしい形相で睨み付けていただなんて、気が付くことができなかったのである。
明日公開の3へ続く → 続き(ここをクリック!)
ちょこ札幌の事務所スタッフの中には、チャットレディ経験者も多数在籍していますので、何か分からない事や不安な事があれば気軽に相談してくださいね♪